
闇の中の歩み
篠原雅武の『空間のために』(2011)を今さらながら読んだ。この本では、時間的プロセスのなかでの社会変容という観点から捉えられてきた世界を、空間から捉えそうとするものである。空間は、単に物理的なものではなく、私たちが感じ、考え、生活する場所を指している。この本が問題とするのは、そうした空間の荒廃である。
2018年もそろそろ終わりに近づくだけでなく、平成という時代も間もなく終わろうとしている。今年を振り返り、また、平成という時代に育った者の一人として、この時代は、“まったくひどいもの”あったように思っている。しかし、そもそも“いい時代”についても具体的なイメージを持っていない「ロスト・ジェネレーション」よりも少し後に生まれた(ポスト・ロスジェネ?)世代として、何が終わり、何が始まろうとしているのかも、よくわからないのだが、篠原の言っている空間の荒廃ということについては、その感覚はわかるような気がする。
その感覚とは何だろうか、と少し考えてみると、“ああ、もうすでに何かが終わってしまったのだな”という確信のようなもの、ストンと腑に落ちるような感覚なのではないかと思う。
思想や哲学、社会批評など、「僕たちはどこから来て、どこへ行くのか」というようなことを問うていて、何かその問いが実感と合っていないような違和感を持ち続けている。“そもそも「どこから来て」というようなことが確たるものとして、僕は言えるのだろうか”というようなためらいだ。それでも、空間の荒廃を目にして、何か「僕たちはどこから来て、どこへ行くのか」と問わなければならないような焦燥感にも駆られてしまう。それでも「どこから来て」というような問いが、空間の荒廃が当たり前になった情景の前で虚空をなぞるように思えてしまう。

だから、「どこから来て、どこへ行くのか」ということを力んで問うてしまうことを、いったんやめにしたいと思いもする。しかし、何も問わないということではない。大上段に振るった問いをいったん棚上げにして、「何がどのように終わってしまったのか」を眺めてみたいと思うようになった。そうして眺めているうちに、なにかこう、じわっと「何かが始まっている」という予感のような、感覚のような、希望のようなものに、少しでも触れられたら、と思う。
これは、「歴史の暮れ方」のような眺め方とは若干違う。林達夫は、同タイトルの著のなかで、歴史を明確に終わりつつあるものとして認識し、そこから距離をとる(ディタッチメント)知識人の姿勢を明確に打ち出すことが可能であった。そこには、大きな流れとしての「歴史」が否定的なかたちであれ、残存している。しかし、「歴史」を規定する大きな経済・社会・政治の文脈が「暮れ」を超えて、すでに「闇」のなかへと落ち込んでしまったとき、そこからいかに距離を取ればよいか、という問いを超えて、問わなければならないのではないかとも思う。それは、「夜はいかに明けるか」というような問いに近づいていると思える。
思えば、20世紀という時代は、そういう「闇夜」へと吸い込まれていく時代だったのではないか、とも思えてくる。それは、「何かが終わってしまった」という感覚とともに人々が歩みを進めた時代でもあったのだ。そこには、「暮れ方」という美しい薄明かりもないような時代へと続く道があったのだ。そして、「美しい薄明かりもないような時代」が現在なのではないか。
ここで、闇のなかの歩みを、盲者のように振り返り、ただ聞き耳を立ててみるような構えも必要だろう。

19世紀の終わりと根なしの近代
《根を絶たれたということは、他者によって認められ、保護された場所を世界にもっていないということである。余計者ということは、世界にまったく属していないことを意味する》(アレント『全体主義の起源3』:320)
哲学者のハンナ・アーレントは、かつて、全体主義という20世紀に特有の極端な暴力的な政治が生み出された背景に、「根を絶たれたということ」を見出した。この根無しの状態を、フランス語で「デラシネ(déraciné)」と呼ぶ。ここで「余計者」とは、20世紀の総力戦、そこで生じるジェノサイド、また暴力によって故郷を喪失した難民たちを指している(典型的には、ユダヤ人がその象徴である)。
だが、殲滅的な戦争という極限的なケースだけでなく、近代社会は、潜在的には、そこで生きるすべての人々を「根無し」にする力を持っている。それは、諸個人の力では、コントロールしがたいような組織化の果てに生じるものだろう。戦争や強制収容所だけでなく、日常的にバイアスのかけられたテレビメディアやネットメディア、世論や物価、あるいは雇用や失業に関する統計に一喜一憂すること、大量の情報が飛び交う状況、また、科学技術の力によって生活のかたちが刻々と変えられていくこと。政治に力を及ぼすのは、自分自身の国ではない国際情勢や多国籍企業であり、また、あかの他人であるはずの政治家の過激な発言に国のかじ取りをゆだねてしまうこと、官僚機構が鉛筆をなめながら公表されたり隠蔽されたりする公的情報・・・・・・もはや、諸個人の力ではどうしようもないような外的な組織の論理が社会を方向づけ、また、ずるずると閉塞する状況へと人々を運んでいく。

歴史家のエリック・ホブズボームは、20世紀を「極端さの時代」(Age of Extreme)と名づけた。彼は、その時代の始まりを1914年の第一次世界大戦のはじまりに定め、1991年の冷戦構造の解体に終点を定め、その期間を「短い20世紀」と概念化した(それに対して、19世紀は、1789年から1914年に時期区分され「長い19世紀」と概念化される)。第一次世界大戦は、19世紀的な「近代」への信仰を掘り崩す出来事であった。19世紀的な「近代」への信仰とは、例えば、ドイツの哲学者ヘーゲルが『精神現象学』などで定式化したような「精神」の発展過程である。彼によれば、人間は、家族のもとで育ち、市民社会へと仲間入りし、そこで社会関係を学び、個人になり、その後、国家のもとで自己同一性を確立することで、歴史的にみて成熟した人格を完成させる。

しかしながら、「長い20世紀」の始まりは、諸個人の成熟を可能にするはずの国家同士の戦争によって、また、最新鋭の兵器によって、大量の死者を生み出したことで、ヘーゲルの「長い19世紀」に終止符を打った。第一次世界大戦が終わろうとする前に、シュペングラーが『西洋の没落』を書いたのは、「極端さの時代」が成熟の近代への信仰が虚構にすぎなかったことを象徴している。
この延長線上で生じた第二次世界大戦は、原子力爆弾の広島、長崎への投下というかたちで、殲滅戦争の「極端さ」を示すかたちで終局を迎えただけでなく、ユダヤ人の大量虐殺、あるいは、日本軍の南京における蛮行、今日問題として再浮上している「徴用工」(それがいかなるかたちで徴募されたものであれ、過酷な強制労働を伴う奴隷制)、731部隊など、それぞれが比較を絶するような「悪」の事態によってその後の歴史に消せない傷を残すことになった。

21世紀に生きる私たちは、なかば無意識に、もはや、こうした蛮行や大量破壊は起こりえないと、高をくくることができるだろうか。たしかに、当時のような大量破壊の形態は、過去のものとなったかもしれないが、いまや、湾岸戦争の「ニンテンドー・ウォー」に始まり、近年のアフガニスタンやイラク、あるいはイエメンなどで使用される無人爆撃機など、「極端な時代」を形づくる大きな要素としてのテクノロジーの進歩による大量破壊は十分に可能になっている。さらには、これはWikipedia(「無人航空機」)によるものであるが、「無人の航空機を遠隔操縦するという発想は第一次世界大戦中からあり、第二次世界大戦時から研究が本格化した」とされている。当時は、技術やコストの面で限界があり、戦場での応用はされなかったが、それでも、今日の戦争は、いわば「長い20世紀」のはじまりから“夢見られた”ものの延長線上にあることとも言えるだろう。
このように、技術的・科学的な進歩は、「極端さの時代」において、野蛮の領域と背中合わせの関係にある。蛮行が伴わない近代的な技術進歩というのは、「ダイエット・コーラ」だとか、「ヘルシーなジャンク・フード」と言うようなものだろう。
続きでは、科学的精神の延長線上で、なおも、私たちはこの先の時代を見通することができるのか、また、何が終わり、どのように新たな社会の動きへと入っていくことができるのかということを考えてみたい。
(松井信之)

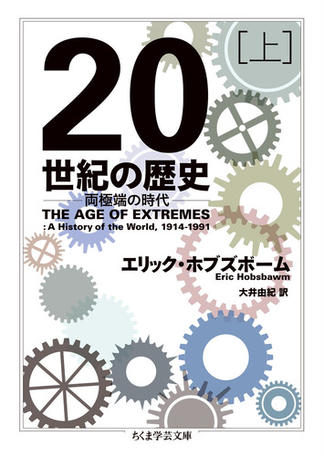
コメントをお書きください