
最近、デヴィッド・グレーバーやマウリツィオ・ラッツァラートなど、「負債」を中心に現代資本主義社会を批判し、その乗り越えを模索する著作を読むことがあり、資本主義批判の潮流に生じている「負債論的転回」とでも呼べる視点の転換がなぜ生じたのかを考えている。
なぜゆえに「負債」という概念が批判の準拠点となり、また、なぜそれが今日において、焦点化されるようになったのか?その意味するところが気になる。
大雑把に言えば、債務システムの強化がポピュリズムのような幻想の政治の勢いを強め、また、それと同時に、国家への権力の集中が生じる中で、さらに債務システムが強化していくという悪循環が「負債論的転回」が思想の領域で生じてきた背景にある。したがって、債務システムを克服することが、今日の幻想の政治からの脱却のカギとなりうるということである。簡単に言えば、幻想の政治を解くカギは、債務システムを問い直す方にあるということである。
しかし、このことは、単に、経済構造を変えれば観念が変わるということではない。むしろ、私たちがどのようなシステムに依存しているのかという問題意識を共有し合い、どのような社会が可能なのかを問い直していくという批評的・政治的・文化的な実践のなかからでしか、そうした問い直しはできないであろう。
「負債」をめぐる問題は、一般的な社会問題においてしばしば目にする。列挙してみれば、ミドル・クラス(中流階級)の崩壊に伴って社会格差が生じ、カードローンの借金に依存する人々が増加していること、リーマンショックで明らかになったような粗悪な住宅ローンにはまり込んで救済されない人々、第三世界の諸国が先進国に負う債務、また、毎年増大し国債によって賄われる国家の歳出予算(日本の2018年の一般会計総額は約98兆円)、あるいは、奨学金のローンなどなど…。
このように羅列してみても、「負債」や「借金」が人々の社会生活に与える大きな影響という問題が前景化してくるのも分かる。だが、それだけではない。すなわち、人々がますます社会問題化している債務や借金に影響されるようになっているというだけでなく、それ以上に今日の「負債論的転回」は、私たちの社会の存立要件(あり方)についてこれまでとは異なる想像力が求められていることを示しているのである。

まず、「負債論的転換」とは、何を意味しているか?ラッツァラートの『〈借金人間〉製造工場』(2012年)では、いわゆる「新自由主義(ネオリベラリズム)」と呼ばれる1970年代後半以降の経済政策の潮流によって生み出された社会の流動化ののちに新たに付け加わった金融経済の高度化が社会を「債権者」と「債務者」に分断を促してきたことが示されている。

「新自由主義」とは、デヴィッド・ハーヴェイの『新自由主義』(2007)によれば、「強力な私的所有権、自由市場、自由貿易を特徴とする制度的枠組みの範囲内で個々人の企業活動の自由とその能力とが無制約に発揮きれることによって人類の富と福利が最も増大する、と主張する政治経済的実践の理論」である。しばしば市場への介入を最小限にした「小さな政府」を支持するのが「新自由主義」であると言われるが、ハーヴェイによれば、実際のところ、国家は、これらの目的に向けて、「制度的枠組みを創出し維持すること」を産業界や資本家らから期待されるという点で、国家の国民への保護的な役割は「小さく」ても、資本家や産業界、また財界にとっては「大きい」政府を支持すると言った方が厳密には正しい。ハーヴェイいわく、「新自由主義」のもとで「私的所有権を保護し、市場の適正な働きを、必要とあらば実力を用いてでも保障するために、軍事的、防衛的、警察的、法的な仕組みや機能をつくりあげなければならない」のである。また、理論という狭義の「新自由主義」ではなく、一般的な現象としてそれを捉えれば、一貫した政策的な原理によって今日の不安定な社会構造が生み出されたというよりも、財界や産業界の力が政策の中心に食い込んでいき、資本家、大企業などの利害によって経済政策や社会政策の方向性が決定されてしまうことで長期的な社会の安定性をいかに確立するかという視点が得られないという問題が挙げられる。

また、労働市場の特徴を挙げれば、新自由主義以後にとくに顕著になってきたことであるが、労働者一人一人に柔軟性・創造性・合理性を求める企業家モデルが浸透してきたことである。このことは、リュック・ボルタンスキーとエヴ・シャペロの『資本主義の新たな精神』(原著1999年)に詳述されている。労働市場の流動化と一人一人に要求される能力水準の高まりという現象は、「負債論的転回」といかに関わっているか?一言でいえば、それらは、他者に何かを負う者と負わない者のあいだの分極化を貨幣を基準にして区別するということにおいて結びついている。言ってしまえば、有能な人間は他者に何も負うことなく生きることができ、無能な人間は他者に依存しなければ生きることができない、という区別が新自由主義経済の成れの果てとして生み出さえた社会だということである。
もっと直截的にいえば、貨幣は誰かに依存しないための社会的ツールとなり、それを持たないことが「無能」や「債務者」としての烙印となるということである。

だが、デヴィッド・グレーバーは、「負債論的転回」は、何もいまに始まったことではなく、人間が大規模集住をすることになって以来このかた、人間社会につきまとう問題であることを『負債論』のなかで強調している。「負債」は、神のもとで、支配者のもとで、また、資本家のもとで、それに従属する人々に植え付けられなければならない意識である。「負債」の観念は、たとえば「わたしの身体は神から与えられたものである」という見方と同様に人類につきまとうものである。たとえば、ヒンドゥー教のブラフマナでも、「負債」とそこからの解放が問題とされている。
しかし、神に負うている人間の生という観念は、そこから完全に解放されることのない「負債」を背負うことを意味する。もし、その負債をすべて返してしまえば、それは死を意味するだろう。神々の祭壇に供される貢物は、こうして「債権者」たる神に対して利子を払うものとして理解され始めた、とグレーバーは言うのである。
では、なぜグレーバーらとともに、ことさら「負債」を強調する必要があるのか?それは、人類社会の条件としての負債感覚内部に生じた「転回」があるからである。それが先に述べたような、負債の関係をすべて数値化して換算する貨幣化が社会全般で生じているという問題である。同時に、ここでは、負債感覚の有無が社会生活において決定的に重要なものとなり、負債感覚を被ることがネガティヴに捉えられるのである。

以上の意味で、新自由主義的な資本主義は、近世ヨーロッパの初期にトマス・ホッブズが『リヴァイアサン』(1651)で描いた「万人の万人に対する闘争」という自然状態のフィクションを現実化したような状況を招いたのである。ホッブズの思考実験では、断片化された(相互に切り離された)諸個人が自己の利益を最大化しようとするなかで一定の秩序(主権者への従属)を最適解として導き出すというものであった。しかしいまや、主権国家の新自由主義下での強権化を前提として、自己利益の最大化をめぐるゼロサムゲームが展開されるのである。主権国家の強権化は、先にも述べたが、市場に対する強権化ではなく、いわゆる「新保守主義」という新たな伝統主義とセットになったポピュリズムをたずさえて、社会を一つに取りまとめようとする一方で、新自由主義政策を貫徹させ、人々への実質的な経済的保護を欠如させた空虚な伝統共同体主義を伴っている。あるいは、ゼロサムゲームのなかで莫大な富を得たものが主権国家の方向を左右するという意味では、自然状態が統治の常態(通常のあり方)として放置され、それによって無秩序化した社会の原因を「伝統」の喪失という空虚な過去への幻想に見出すとも言えるだろう。

ここにおいて、私たちの社会生活は決定的な転換を迫られるだろう。グレーバーは、社会の成立は、「負債」に依拠していると指摘する。
“たとえ暴力に基盤をおいていようと、ある体制な効率よく運営するには、ある種の規則の集合体を設定する必要がある。それらの規則はまったく恣意的でかまわない。それらがどのようなものであろうと問題でないのである。あるいは少なくとも最初の段階ではどうでもいい。問題は、ひとたび負債の観点から物事な枠づけしはじめると、人びとは不可避にだれがたれになにを負っているか、問いはじめてしまうということにある”。(グレーバー『負債論』、14頁)
このことから、債権者/債務者の構造が分極化し、固定化する状況が私たちがいかなる社会を生きているのかをめぐる想像力を決定してしまうということが分かる。ピエール・ルジャンドルというフランスの法人類学者は、『ドグマ人類学総説』(原著1999年)において、社会制度は、人々に「人格(persona)」を与える枠組として、「個の主体的形成」に先行すると言っている。さらに、その先行的な社会制度の性格は、「親子関係システム」を出発点として、「人格」にあらかじめ社会化のための「刻印」を授ける(ルジャンドル『ドグマ人類学総説』、35‐36頁)。
また、ルジャンドルによれば、個人は「親子関係」を基盤にして、より広い社会的文脈の一体性を支えるものとは何かという観念に基づいて、社会的人格を形成していく。その観念は、ルジャンドルの言葉では、「原因対象」へ向けられる(同上、46頁)。その「原因対象」へ向けられた意識を通じて、「文化」や「連続」、あるいは、政治共同体の「創設」を諸個人の信念のなかに社会を取りまとめる「虚構」ないし「ドグマ」として書き込まれるのである。
新自由主義のもとにある社会でも、この条件は変わらないのかもしれない。しかし、先に「新自由主義」と「新保守主義」のタッグが強権を発動するという問題において見たように、「原因対象」へ向けられる意識は、何らかの実体的な支えなく、ますます幻想的なもの・虚構的なものを信じるように仕向けられることが、今日の社会性の成立の条件となっていると言えるだろう。
こうした究極に幻想的な「原因対象」への没入は、グレーバーの負債をめぐる議論とともに考えれば、私たちのアイデンティティ形成にとって深刻な問題を生み出すということが分かる。すなわち、一方で、実際のところ、私たちが社会生活のなかで債権者/債務者という図式に投げ込まれているが、他方で、たとえば「日本人」が「日本人」として負わなければならない過去との連続性を持ち出してくる、ということである。さらには、「新保守主義」の言説が「日本人」であることの他国への優越性を強調するとき、それは、「負債」として歴史を捉えるのではなく、他者に対する「債権者」的な優位性の証として歴史を捉えることを意味する。こうして、実際のところ多くの人々が「負債」の経済構造のなかに投げ込まれているにもかかわらず、政治の虚構的言説のなかで「負債」を何ら負うところのない空虚な「国民」の観念が再生産されるのである。ここでは、負債システムに従属しているにも関わらず、その事実を新保守主義的な言説に没入することで見ないようにするという事態が生じている。
ここでは、もはや自己同一性(アイデンティティ)は問題とされない。むしろ、不快かつ残酷な現実を見ないようにするというネガティヴな快楽のみが、ある人の社会認識を支える、といった類の事態が生じているのである。ここには、「連帯」や「相互依存」によって支えられる「社会」ではなく、ただネガティヴな快楽のみによって成り立つようなつながりしか見出すことができない。
とはいえ、グレーバーとともに言えば、「負債」は、歴史的には、階層構造を支える観念として形成されてきたのであるが、今日の債務システムは、まさに社会生活のなかで目の前に、「負債」が物質化しているとも言えるだろう。私たちは、目の前に債務システムとして差し出された「負債」をどうするか問われているのである。だが、歴史の習性か何かで、幻想のなかに逃げ込もうとしている。
しかし、ここでは、もはや自己同一性(アイデンティティ)は問題とされない。むしろ、不快かつ残酷な現実を見ないようにするというネガティヴな快楽のみが、ある人の社会認識を支える、といった類の事態が生じているのである。ここには、「連帯」や「相互依存」によって支えられる「社会」ではなく、ただネガティヴな快楽のみによって成り立つようなつながりしか見出すことができない。
あらゆる負債に基づく関係が貨幣によって数値化されるシステムを生きること、それでいて、他者に対しては何も負うところのない幻想の歴史を信じること……ここには、無意識に「負債への不快」なるものが捻じれたかたちで表出しているように思える。
ここで最初の問いに戻ろう。なぜゆえに「負債」という概念が批判の準拠点となり、また、なぜそれが今日において、焦点化されるようになったのか?一言で言えば、それが焦点化されるようになったのは、不条理な負債システムの全般化のためであり、「負債論的転回」の意味は、「連帯」や「相互依存」なき「社会」への幻想を振り払うために必要であるという理由を見出すことができるだろう。経済社会システムにおける負債の全般化を転換させることが今日的な課題であり、それと同時に、負債感覚を新たな仕方で社会制度に書き込むことができるようにしなければならない。このとき、「負債」は、「罪責性」との結びつきではなく、連帯の基礎とならなければならないだろう。また、マクロなレベル、ミクロなレベルの双方から、負債の経済システムと歴史への幻想から抜け出すような、実践・思想・議論などの積み重ねが求められるだろう。
言い換えれば、今日の「負債論的転回」においては、経済と政治の両領域において私たちが依存してきた幻想の呪縛からいかにして抜け出すことができるのかということが問われているのである。
(松井信之)

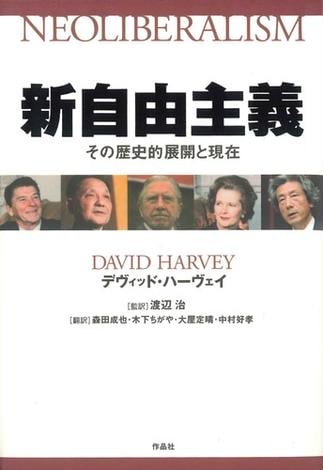
コメントをお書きください